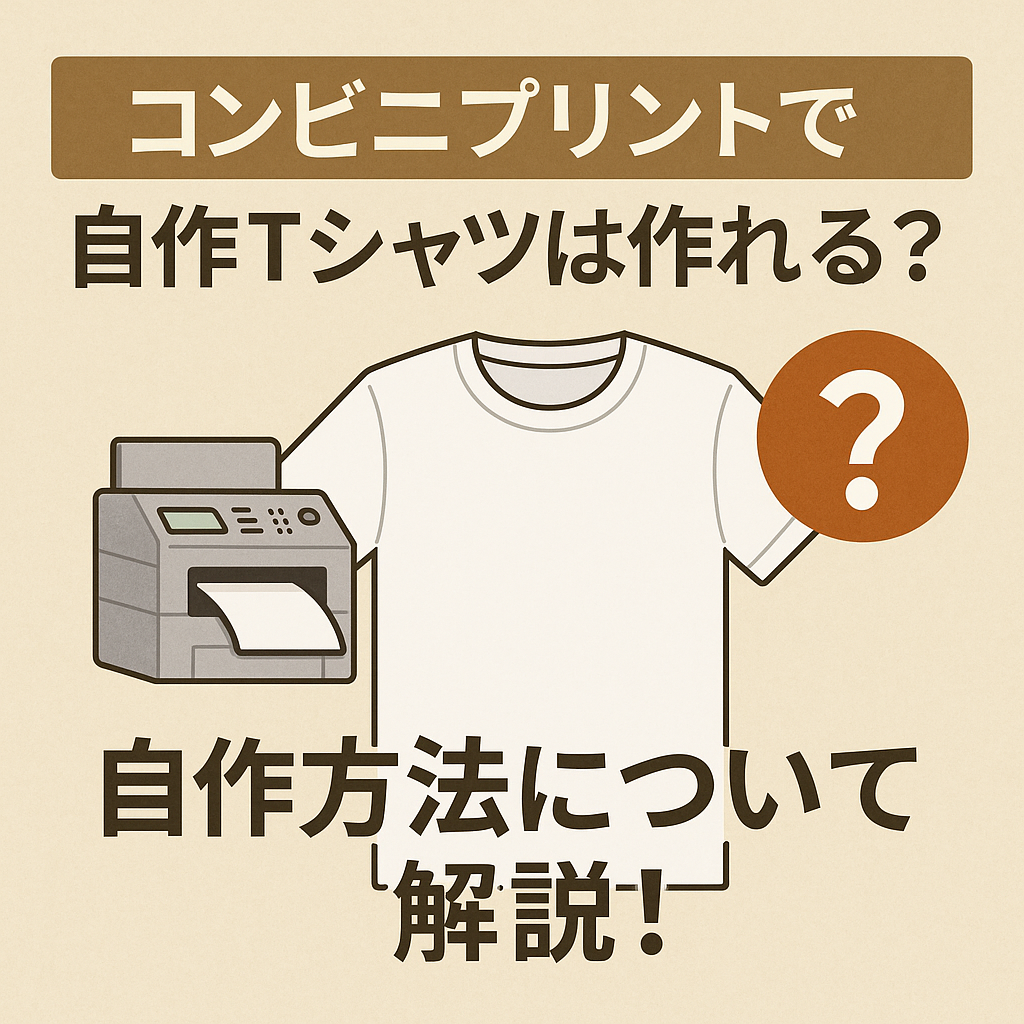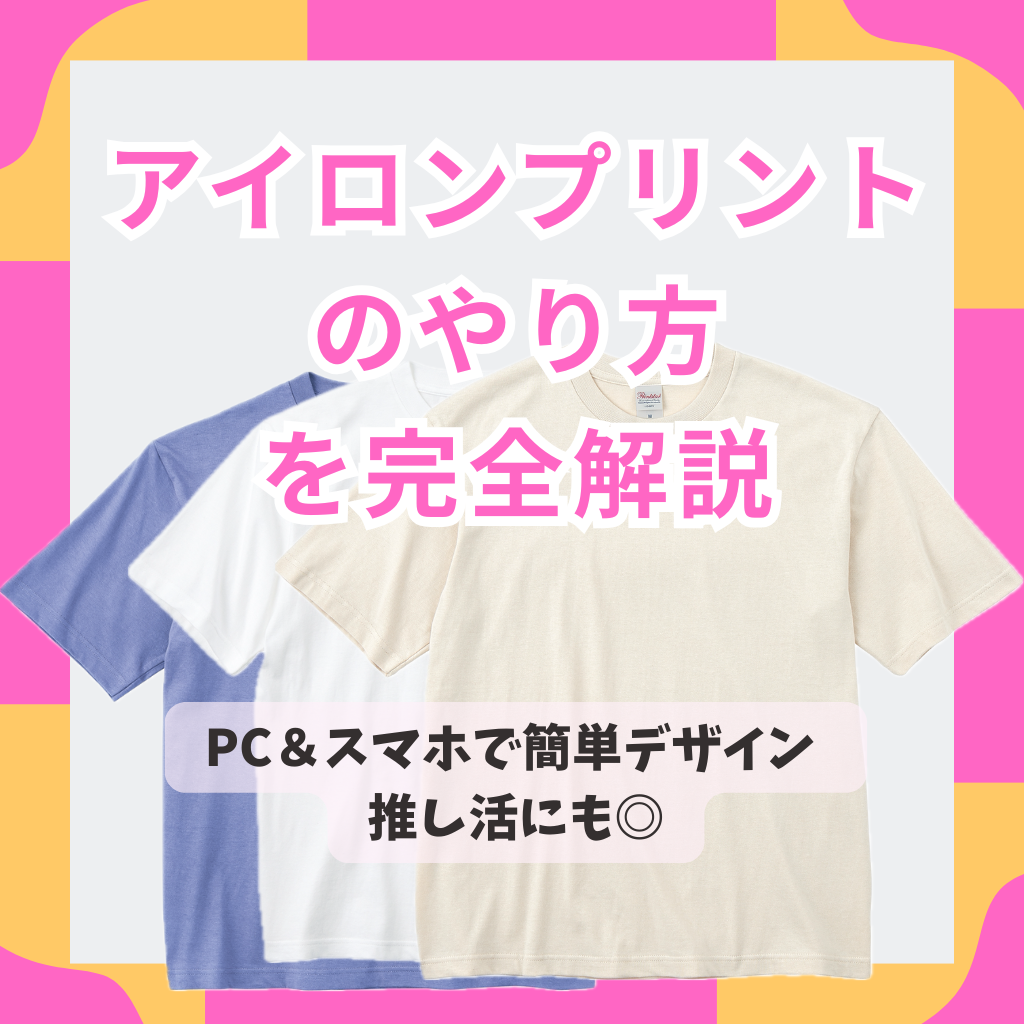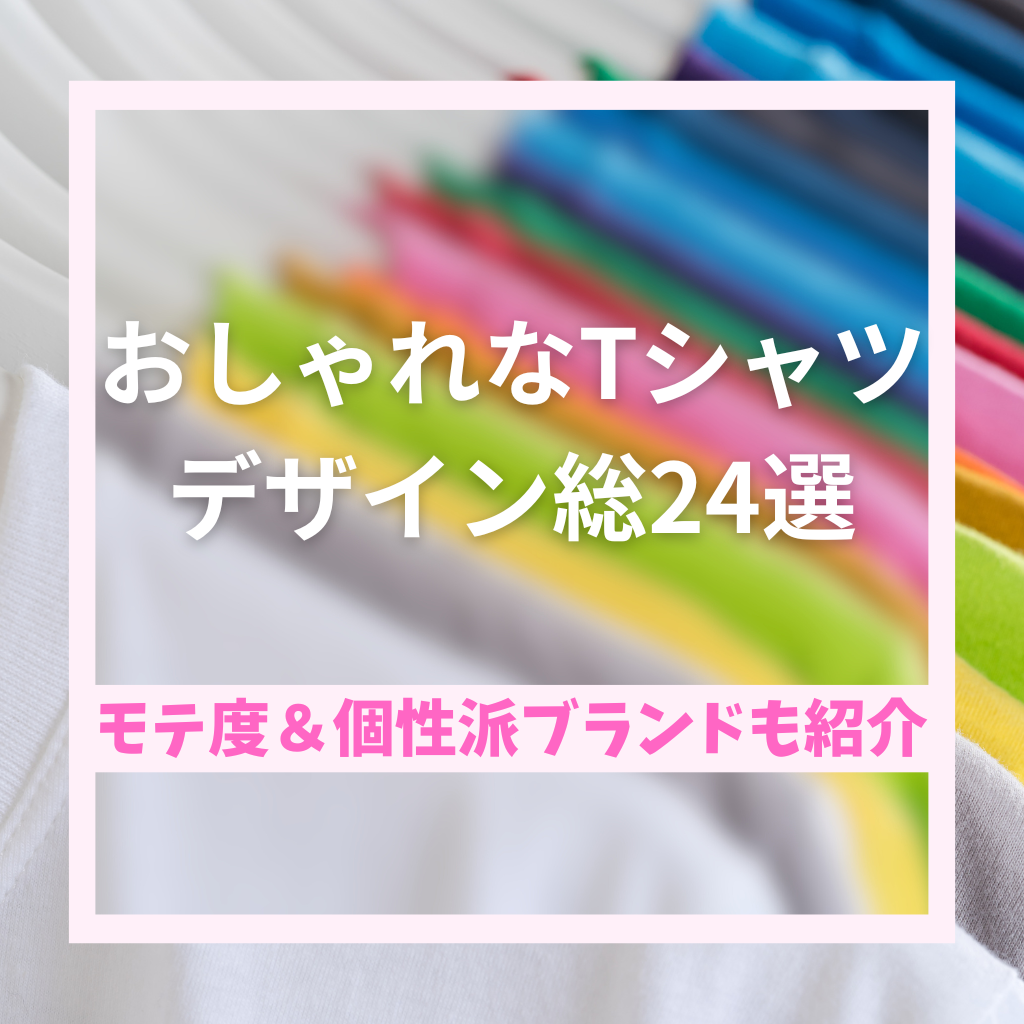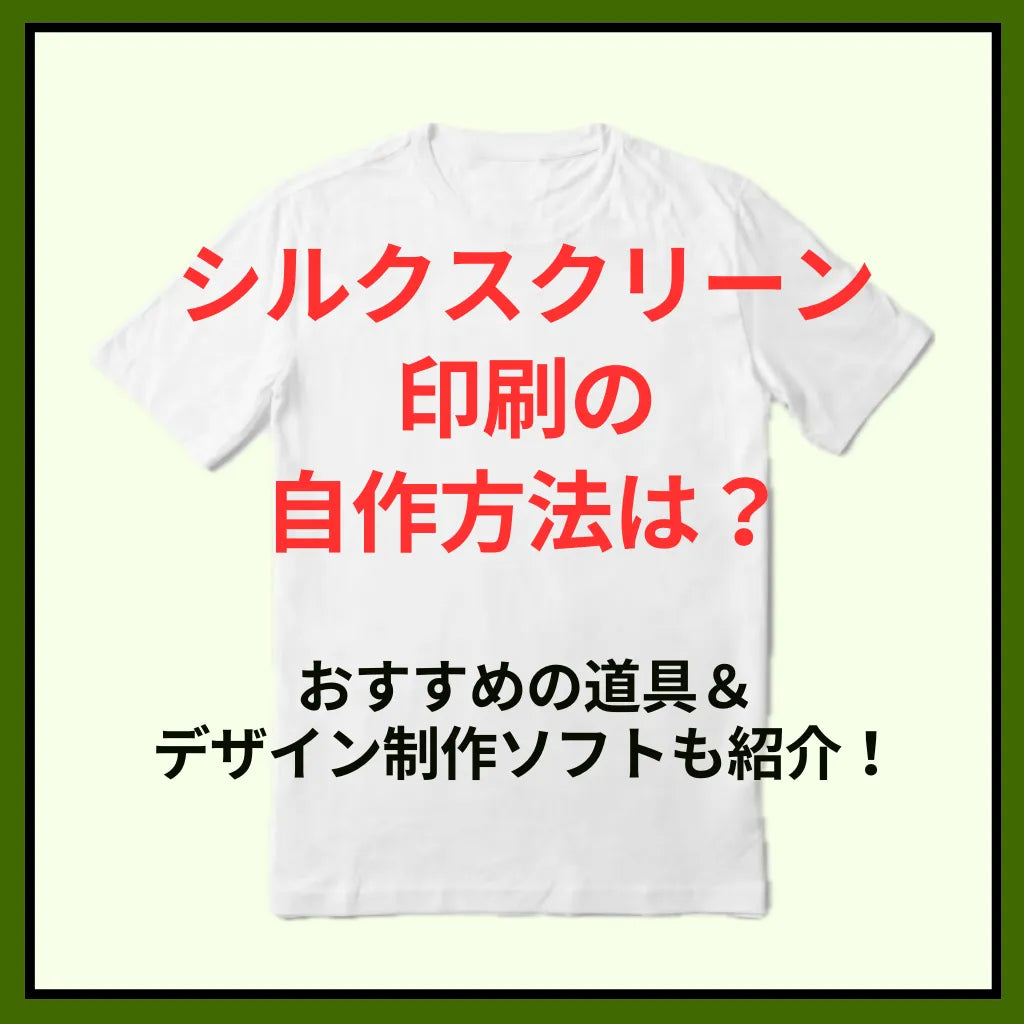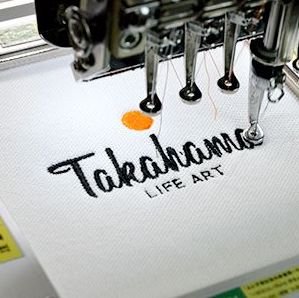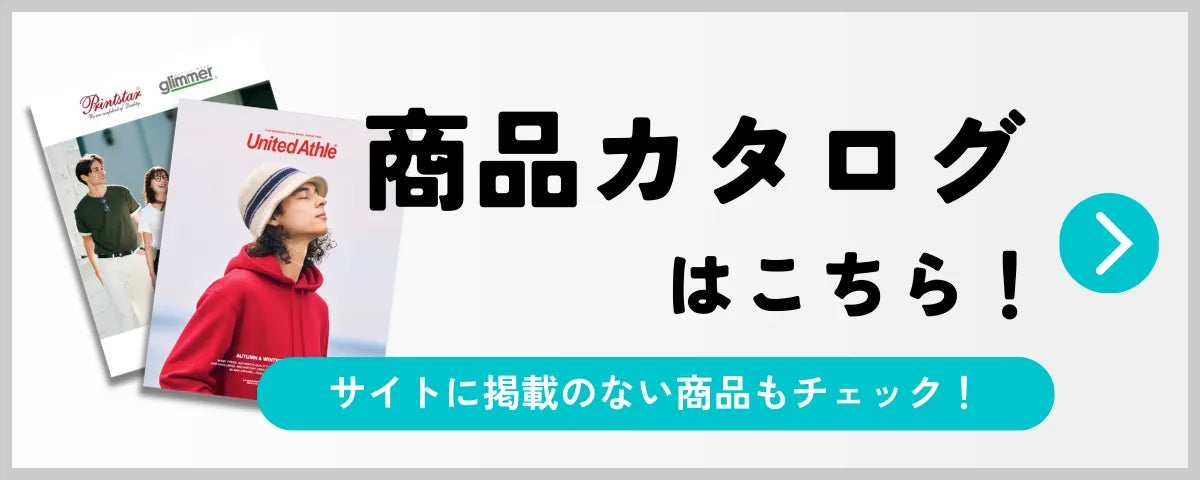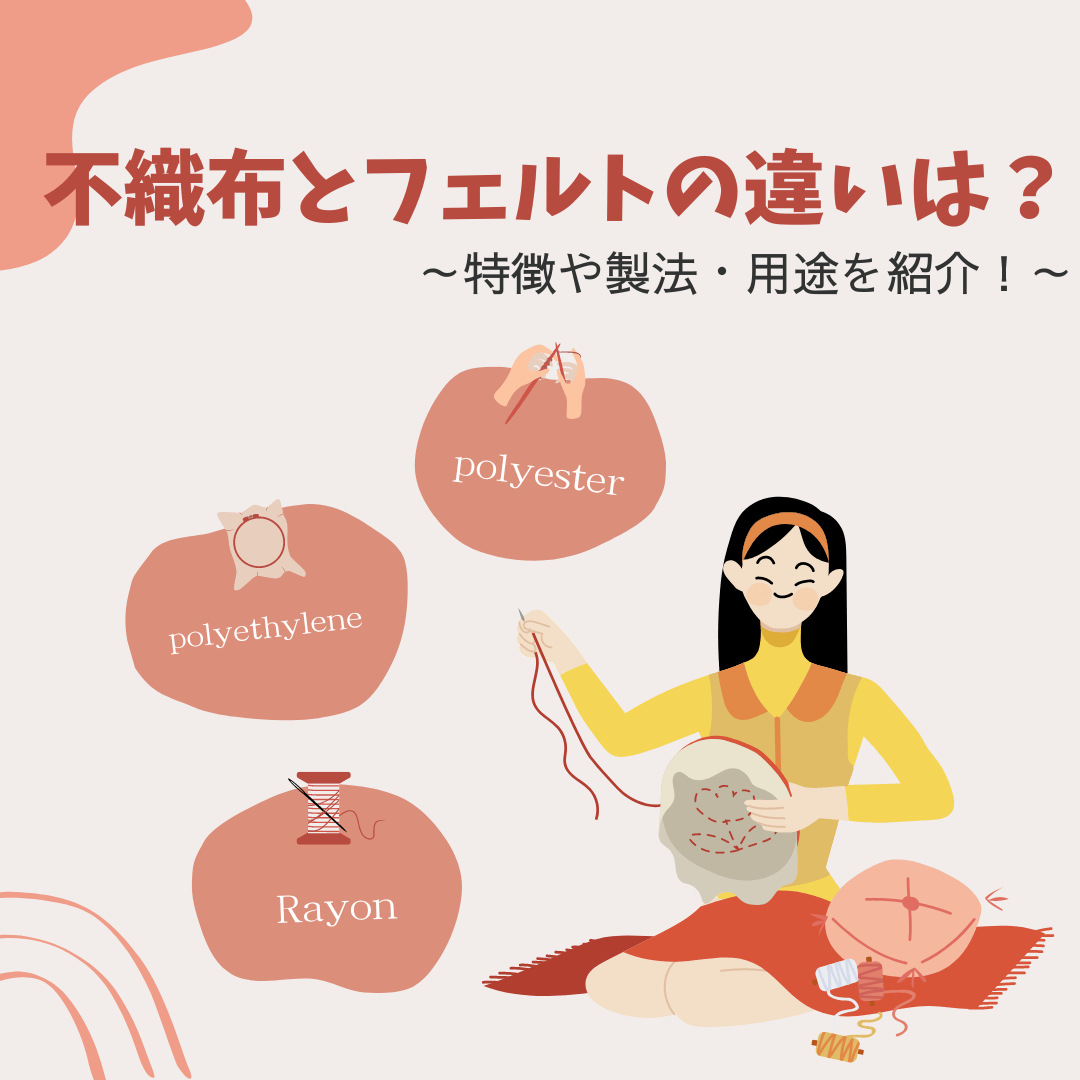
不織布とフェルトは、両方とも「織らない布」です。通常布状のものは織ったり編んだりしますが、不織布・フェルトは全く違う製法で作られます。
では、この2つの生地、いったい何が違うのでしょうか。この記事では不織布・フェルトとはどのような生地なのか、その違いやメリット・デメリット、用途について解説していますので、ぜひ最後までご覧ください。
\ 法人様向けに割引もございます /
不織布の特徴と用途
不織布はその名前の通り「織らずに作る布」です。読み方は「ふしょくふ」になります。
不織布はドイツのフェルト業者が、フェルトの代用品として毛の屑などを接着剤で固めて作ったのが始まりです。まずは、そんな不織布の特徴を解説します。
主な原材料

腐食の原材料として、繊維に加工できるほとんどの物質を使うことが可能です。各繊維にはそれぞれ異なる強みがあります。それらの原料を複数組み合わせることで、用途に応じた機能を持つ不織布を作ることができます。
羊毛などの天然素材も使われる場合がありますが、原料の中でもよく使われるのが、以下のような「化学繊維」です。
| 素材 | 特徴 |
| PET(ポリエステル) |
|
| PP(ポリエチレン) |
|
| レーヨン |
|
上記以外にも強度と耐熱性を併せ持つナイロンや、耐水性のあるビニロン素材など、様々な繊維が使用されます。
製造・加工方法

不織布の製造方法は、大きく分けて2つの工程があります。
繊維を薄いシート状に形成する
この工程にはいくつかの方法があり、例えば「スパンボンド法」は、繊維を溶融して長繊維状に吐き出しながら形成する方法です。他にも高温の空気を当てながら形成する方法や、水と混ぜ漉いて形成する方法などもあります。
繊維同士を結合する工
シートにしただけでは強度が低いので、繊維をしっかりと結合して強度を上げます。シートを形成する工程と同様に、結合にも様々なやり方があります。
接着剤を吹き付ける「ケミカルボンド法」や針をを使って機械的に結合する「ニードルパンチ法」、高圧水流を利用した「スパンレース法」などが代表的な方法です。使用できる繊維と同様に製法を数多くあるため、原材料や目的に合わせて選択できます。
主な用途

これまでに説明したように、不織布は原材料や製法を変えることで様々な機能性を備えています。そのため幅広い製品に応用可能です。例えば以下のような製品に使用されます。
- 医療用品(手術着、ガーゼなど)
- 衛生用品(オムツ、マスク、サニタリーナプキンなど)
- 衣料品(婦人・紳士服の副資材、防寒着の中綿など)
- 建築用品(養生シート、吸音ボート、霜などの防止シートなど)
- フィルター(空気清浄機や防塵フィルターなど)
マスクや衣類、空気清浄機のフィルターなど、私たちの暮らしにかかせないものにも使われています。上記はあくまでも一例です。その他にも農業用品や自動車用品など、多くの場面で不織布が使われています。
メリット・デメリット

不織布は素材を組み合わせており機能性が高く、幅広い用途に使えます。この特徴を活かして、医療用品や衛生用品、衣類など多くの場面で活躍できています。複数の素材を簡単に組み合わせて汎用性を高めるだけでなく、大量生産が可能なため安価で生産できるのもメリットの1つです。
一方で、デメリットはやはりしっかりと織られた布よりは強度が低い点です。また、繊維の組み合わせで機能が決まるため、布によっては熱に弱い、耐水性が低いなど弱点が存在するでしょう。化学繊維なら静電気が起きやすい、天然素材なら縮みやすい、シワになりやすいなどのデメリットがあります。
フェルトの特徴と用途
フェルトは動物の繊維を圧縮してシート状にしたものです。また、動物の毛だけではなく、ポリエステルなどの化学繊維を使った製品も存在します。
フェルトは、非常に長い歴史を持つ布で、遺跡からは紀元前のものとされるフェルトが発見されています。現存する日本最古のフェルトは奈良の正倉院にある「毛氈」で、なんと1300年ほど前のものなのです。
主な原材料

化学繊維や麻を使ったものもありますが、主な原材料は羊毛などの動物繊維です。羊毛が持つ染色性や撥水性、保湿・吸湿・放湿性を活かした生地を作れます。
製造・加工方法
石けん水のようなアルカリ性の水溶液を毛に含ませ、熱や圧力を加えて繊維同士を絡ませることで形成します。アルカリ性の水溶液で湿らせることで、毛のキューティクルが開いて噛み合い、熱や圧力によって絡まって離れなくなります。
この加工方法を「縮絨」といい、縮絨をすることで組織間がよりしっかりと結合し、強度を高めることが可能です。なお、この製法で作られる「フェルト」は、JIS(日本工業規格)の定義において「不織布」に含まれないと決められています。
また、羊毛フェルトは、ご家庭でも作成することが可能です。台所用洗剤などを加えたお湯(42~45度程度)を毛にかけ、何度もこすって圧力をかけて作成します。
主な用途

フェルトの持つ保湿性などから、以下の用途で使われています。
- 帽子やカバンなどの衣料品
- 絨毯やカーペット
- ピアノのハンマーのカバー
その他にも産業用や工業製品など、幅広い用途で使われています。その他フェルトを使ってハンドメイドで制作されている方もいます。製作するものは人形やキーホルダー、マスコットなど。
フェルト素材の優しいあたたかみのある雰囲気や優しい肌触りは、子どもへのプレゼントやインテリアとしても活躍するでしょう。
メリット・デメリット

フェルトは断熱、保温、クッション性に優れている点が挙げられます。優しい肌触りも特徴的ですね。また、防音性もあるため、ピアノのハンマーのカバーにも採用されています。手芸などに使えるフェルトシートは、100均や通販などで容易に入手しやすいです。100均などでも購入可能です。
デメリットとしては引っ張りや摩擦に弱く、伸縮性がありません。また、ご家庭でフェルト製品を取り扱う場合、洗濯機を使用することで摩擦が生じて縮んでしまいます。縮みを防ぐためには手洗いで優しく洗う必要があり、フェェルトの製品は丁寧に取り扱いましょう。
フェルトのアイテムに刺繍デザインがおすすめ
優しい風合いのフェルトは様々なアイテム作りに使われ、なかには自分でフェルトのアイテムにデザインをプラスすることもあります。オリジナルなフェルトは自然と愛着が湧くので、フェルトのアイテムを持っている場合はぜひp理事なるフェルトを作ってみてください。
オリジナルフェルトアイテムは「刺繍」でデザインをプラス

刺繍は独特な高級感や風合いが特徴的なデザイン方法で、耐久性が高いことも魅力です。フェルトのアイテムにデザインをプラスする時にもおすすめで、フェルトアイテムに一層の愛着が湧きます。
当サイト・タカハマライフアートでは刺繍を使ったアイテム作りの実績が豊富で、これまで様々なアイテムに刺繍でデザインをプラスしてきました。カラフルな糸で版を使わず刺繍を施すので、再現性・デザイン性のあるデザインをプラス可能です。
オーダーに指定のデザイン案を提示いただければ、タカハマライフアートの職人が刺繍デザインをプラスするのでぜひ検討してみてくださいね。
デザインのオーダー方法

タカハマライフアートでは見積りフォームなどを活用して、お持ちのフェルトにオリジナルデザインをプラスできます。公式の見積もりフォーム・Instagram・LINEなどから、刺繍でデザインしたい旨を気軽に相談ください。
デザインの方向性や見積り額、納品日などをタカハマライフアートのスタッフ・職人たちと相談しながら、とっておきのオリジナルフェルトアイテムを作ってみてはいかがですか?
不織布とフェルトの違いまとめ
2つの違いは、以下の通りです。
- 主な原材料
→不織布は化学繊維
→フェルトは動物繊維
- 製造方法
→不織布は機械などで薄いシート状にし、針や接着剤を使って繊維を結合
→フェルトはアルカリ性溶液を含ませた毛に圧力を加えて形成
- 機能性
→不織布は生地の組み合わせ次第で機能性を変えられる
→フェルトは保湿性・耐熱性・防音性に優れている
フェルトと不織布は「織らない」という点で同じですが具体的な製法や原材料、その生地がもつメリットやデメリット、用途は異なります。両方の特性を理解して、より用途に合う生地を利用しましょう。